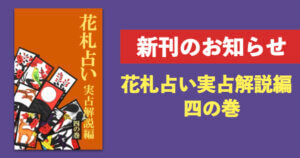「あの日失敗したのは、僕の星回り的に“試練の年”だったから仕方ないんだ」
「遅刻したのも、生まれつき“時間にルーズになりやすい星”のもとに生まれてるんだよね」
「だって、生まれた瞬間の星の配置って、もう偶然じゃなくて必然でしょ?」
「恋愛がうまくいかなかったのは、生年月日的に“縁が薄い時期”って決まってたからだよ」
「計画が崩れたのも、“最初からそうなる運命”だったんだ」
「お金のトラブルは、生まれつき“金運に波がある星”だから、避けられないんだよ。」
「仕事での失敗も、生年月日で見れば“試される宿命”の年に当たってるだけなんだ」
「健康を崩したのも、もう生まれたときから“体が無理しやすい星”に組み込まれてたんだよね」
こういった「生まれつき」「先天的」「運命論」「そういう星のもとに生まれた」「こういう親に生まれたから」といった理由付けをするのはもう諦めたほうがいいのかもしれません…
どうして!そんなことはない!と思う人はエピゲノム、エピジェネティクスについて調べてみてください。この本が比較的入門本としてわかりやすかったので、おすすめです。
エピゲノムと生命
https://amzn.to/3Ji67Pt
生年月日を使う占いのほとんどが「運命や性質は生まれた瞬間に決定している」という前提があります。これは前成説(ぜんせいせつ)の考えの拡大解釈的な前提になります(以前、このような記事も書いています)。
「なんで占うときに生年月日を使わないんですか?」
https://nishikei.jp/nishikei-pon-uranai/40203/
もちろん生まれた場所や環境自体を変化させることが出来なかった時代(生まれた土地や家柄が固定的だった場合)は、これらの言説でも通用したのかもしれませんが、現代の日本では比較的環境を変化させることが容易です。
「エピゲノムと生命」には一卵性双生児の病気の例も記載されており、リウマチ、脳卒中、クローン病、乳がん、多発性硬化症、糖尿病、高血圧症などの症状は遺伝的要素が50%以下になり、環境的要素のほうが発症に寄与すると書かれています。
つまり、病気すら「生まれつき」とか「親からの遺伝で」では説明がつかないものもたくさん出てきおり、環境的要因によって運命は大きく左右されることになります。
過去の記事でも何度か書いているのですが、家相や墓相や家系などを研究していると、環境的要因のほうが大きいのではと感じることがよくあります。それは良くも悪くもであり、うまく活用できている人はそれで比較的優位になり、不利なまま認識を変えずに固定的になっている場合はより不利になっていくのです。そして、後者の人の多くが、冒頭に書いたようなことをよく言いがちです。でも、いろんなことが明らかになってきて、その言いわけがもう通用しないよねってことなんです。
平凡な親から優れた子供が生まれるという意味の「鳶が鷹を産む」ということわざがありますが、このことわざも消滅するかもしれません。優れた親から平凡な子が生まれるパターン「鷹が鳶を産む」ということも十分ありえるので、20-30年後に生きる人たちはこのことわざを見て「???」となるかもしれません。
エピジェネティクスの立場は「環境的要素が全て!」と言っているわけではありませんし、何世代か飛ばして発現する遺伝子もあるので、親や生まれのことを全く無視しているわけではありません。しかし、エピジェネティクスについて知ると「親が全て!」「生まれが全て!」「運命は生まれたときから決まっている!」とは恥ずかしくて大きな声では言えなくなります。
何かうまくいかないことがあったときに、どう環境を変えるのか。場をどう変えるのか。その人物と場との相関についてより多くのデータを蓄積していく必要がありますし、人間関係も「人間が作り出す場」と考えるのであれば、従来の占いがもっている「関係性をシンボルなどを用いて分析する手法」も違った形で役に立つ場面が出てくると思います。ただ、現代では「立場」や「関係性」が固定的ではなかったりするので、初期段階としてはテンプレート的な利用が理想的と言えるかもしれません。
「自分はバカだ!」「あいつはバカだ!」「あの人はすごい!」「自分はすごい!」といった決めつけみたいなものが、いろんなことが明らかになるにつれて、どう見ても「愚かな行為」になっていくので、気をつけましょう。
反対に環境や場を変えることで、より快適に生きられる可能性が高まってきているわけですし、「可変性(変えられる部分)」に目を向けたほうが、どう見てもメリットが大きいと思います。
最近思うのは、自分は場や環境を変えるときの「ちょっとしたきっかけ」みたいな存在になっているような気がします。「ちょっと変わる」だけで、流れって変わるんですよね。
にしけい