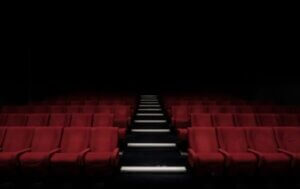いきなり「このお餅、すごいでしょ!最強なんだよ!」と言われたら、びっくりしますよね。
何がすごいのか?
何が最強なのか?
他のお餅に比べてどうなのか?
そのお餅の素晴らしさを理解するためには、「背景」や「順序立てた説明」が必要です。
研究論文でも必ず「研究背景」を書きます。
研究背景は自分たちが行った研究の何が新しいのか?何が素晴らしいのか?といったことを伝える上での土台です。これがないと、いくらエビデンスやデータが揃っていても素晴らしさが伝わらず、評価されません。
美術やアートの本を読んでいても、度々同じようなことが書かれています。
“Most works of art are more valuable when considered within appropriate contexts.”
(ほとんどの芸術作品は、適切な文脈の中で考察されるとき、より価値を持つ。)“…consideration of works in appropriate contexts changes the subject’s experience of the work…”
(作品を適切な文脈の中で考察することは、鑑賞者の作品体験そのものを変化させる。)David Clowney, Art in Context: Understanding Aesthetic Value (State University of New York Press, 2011)
文脈(倫理的・政治的・宗教的・社会的背景など)を考慮することで新しい価値が生まれ、それが評価を生み出します。お恥ずかしいお話ですが、僕は38歳にしてようやくこの文脈を加味した情報の重要性に気がつきました。
googleも文脈を加味した「新しい情報」を求めている
先日、SEO(Search Engine Optimization 検索最適化)に関するお仕事をされている方と話す機会がありました。googleは「新しい情報や体験」を評価する…というお話を聞いて、僕は嬉しくなりました。しかし、そのためにはただ新しさを訴求するだけではなく文脈や検索者が欲しい情報を加味している必要があるらしいのです。
つまり、googleもアートや芸術と同じで、何らかの背景を踏まえた上での新規性を評価してくれるわけですが、この「何らかの背景」の部分をきちんと書かないと、「ただのデタラメ情報」として判断してしまうらしいのです。
冒頭の「このお餅、すごいでしょ!最強なんだよ!」ということをやっていたのは自分で、もっと丁寧に分かりやすく順序立てて物事を説明すべきでした。
このブログや書籍を長年追い続けてくださる方々には、僕が特定の考えに至った経緯が伝わっているかもしれませんが、そうではない方には説明が必要です。
長年の読者の方々に甘えていたなと反省していますし、発見に対する興奮が先走るがあまり、発見したことのみを主張する乱暴な本も数々作ってきました。ついてこれる人だけついてこればいい。そういった読み手に対する甘えがありました。
『Hard Things, Simple Words (むずかしいことを、やさしい言葉で)』
今、YoutubeやInstagramの動画を投稿する中で、撮影者の妻から「それってどういうこと?」「○○って何?」といった質問が投げかけられます。ついつい専門用語や誰もが知らない言葉を使っているし、そういった言葉に逃げていたのかもしれません。
シンプルで簡単な言葉で説明するためには、それについてよく理解している必要があります。「わからない人がわるい」「なんで良さをわかってくれない」「わかってくれる人だけがわかればいい」という感情は話し手の柔軟性が足りない状態で起きます。柔軟性が足りないから、それについて理解が深まっていないし、理解が深まっていないからシンプルに説明することが難しいのです。
誰かに伝わるようにわかりやすく説明するためには、自分自身の固定観念を壊す必要があります。「AはBだ!」という頑な状態では、わかりやすい表現は生まれてきません。「AはCかもしれない」「切り口を変えるとDと似ているかもしれない」といった柔軟性があってはじめて「やさしい言葉」が生まれてきます。
今後は『Hard Things, Simple Words (むずかしいことを、やさしい言葉で)』 を心がけていきたいと思います。
にしけい