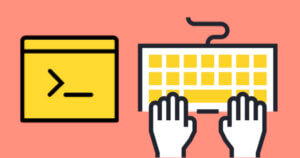「欲」がどうやって生まれるかというと、境界性から生じます。特定の範囲を限定する境界性が発生すると、「有」と「無」という状態が生まれます。もし、有るのか無いのかはっきりしていない状態だと、欲することは出来ません。「有」だけの世界しか知らなかったら、それを欲する必要はありません。「無」だけの世界しか知らなかったら、それを欲することが出来ません。「有」と「無」という両方が存在するから「欲」が生まれるのです。「有」と「無」の境界性が強く固定されればされるほど、欲が強くなり、欲深くなります。格差が大きくなっていると感じるほど、欲は強くなりますし、欲が強くなるということは格差が大きくなっていると感じているということです。
これと同じような仕組みで、「感情」も境界性によって生じます。特定の範囲を限定する境界性(イメージ)が発生し、外界からの何かがその範囲内に入っている状態を「快」で、入っていない状態を「不快」になります。喜び、悲しみ、苦しみ、怒りといった感情を分類する必要はなくて、快-不快でほぼ説明ができると思います。不快度もこのイメージの範囲の限定度が狭くて固定されればされるほど、強くなり、頻繁に起きるようになります。丸が小さいほど、不快に該当する確率が高くなり、丸が大きいと快に該当する確率が高くなります。
丸が大きくても小さくてもいいのですが、固定すると厄介です。なぜなら軽さがなくなるからです。上(外)に向かうには「軽さ」が必要なんです。「軽さ」ほど「重要」な概念はありませんし、軽さは言い換えると、可変性や柔軟性を意味します。なので、丸が大きくなったり小さくなったり、境界性をぐにゃぐにゃとミミズのように変えられるほうが上(外)に出ることが出来ます。風や空気は軽いですよね。そして、風や空気はどこまでも突き抜ける・突き通ることが出来ます。軽いことは軽率で軽んじられるし、重いことは重視され重んじられるわけですが、そうではないんです。本当はどう見ても、軽さのほうが大事なんですね。
「巠」のためには、可変性を高める柔軟性が必要になります。最近、それがわかってきたので、やっぱり呼吸は大事だなと再認識しつつあります。何周もまわってようやく意味や価値がわかることもあって、ヨガはすごいなと改めて実感しています。
にしけい