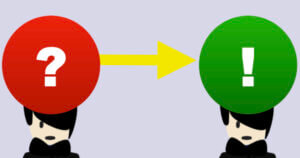感情の機能と感情的になりやすい時期の行動指針についての考察
https://nishikei.jp/nishikei-pon-mind/52265/
先日書いたこの記事からさらに思索が進み、他の知見と合わさって漸く一つの答えが見えてきました。
これまで僕は「快-不快」という感情軸の様なものを用いていましたが、これ自体が感情を優先していることに気づいたのです。大きく分けて人間は本能・感情・知性の3つを駆使しながら生きています。感情は哺乳類や類人猿が持つ機能であり、「範囲の限定」が主目的です。特定の人物・集団・瞬間を限定するために生み出された機能のようで、それによって飛躍的に効率化が行われることになります。しかし、これによる弊害もあります。本来は生存率を高めるために生み出されたはずの感情という機能が過剰に働くと、本能や知性の領域まで侵食し、選択肢や生存の可能性を低下させる可能性があります。反対に言うと、感情の機能が過剰に働いている状態でも生存できるということは、環境的にかなり恵まれていることの裏返しでもあります。何度も申し上げますように、感情は範囲の限定が目的であり、選択肢を減らし、柔軟性を低下させることにつながるからです。
特定の群れの中で安定・安全に過ごすことができるようになると、その状態を保持したほうが生存に有利なため、感情が過剰に働くようになります。この感情のコントロールできるのが、「知性」です。感情の外側にあるようなイメージです。僕はこれまでなぜスーツを着るのか、織り目正しくきちんとすることが「良し」とされるのか、よくわかりませんでした。しかし、ようやく僕の中でひとつの答えが見えてきました。
なぜ「きちんとする」のか、そしてそれを他者に示すのか。それは「感情をコントロールしていること」を示すことにつながります。様々な感情がありますが、大別して「快-不快」に分けることが出来ます。多くの人たちが、この「快-不快」に振り回されます。本能の領域をコントロールするのも感情なのですが、この感情によって支配された状態は危険な状態でもあります。感情が過剰になると、怠惰・やる気が起きない・退廃・破滅といった状態を生み出します。「なぜうまくいかないのか?」の答えのほとんどが「感情」によるものだったりします。過剰に範囲を限定することで、自ら選択肢や機能を抑制しているわけです。
この感情をコントロールすることが「知性」です。「やる気が起きない」「嫌だからやらない」「むかつくから話を聞きたくない」「快楽に中毒的になる」といった感情による弊害を抑制するものが知性なのです。なので、他者に対して「きちんとしているところ」を示すことは、「私は感情をコントロールできていますよ」ということのアピールになり、それによって感情過剰による弊害が起きにくいことを示すことにつながります。
この考えは間違っているかもしれませんし、そのようなことを考えなくても知性的な行動(感情を抑制すること)を実践している方々もたくさんいます。ただ、より多くの選択肢を得ている人と、失ってしまう人の違いのひとつに、「感情をコントロールできているか」という要素があるのではないでしょうか。様々な方々を観察させて頂く機会があるのですが、割とこの要素によって説明できることが多いなと感じます。
ということで、僕も「感情」をコントロールすることで、自分がどのように変化していくのかを実験してみたいと思います。快不快をコントロールできたことで快が得られるループを脳内に形成することが出来れば、様々な選択肢が生まれ柔軟性が増すのではないかなと予想しています。僕の中に「知性による感情コントロールゲーム」が新発売したので、遊んでみようと思います。こうして毎日ブログを書き続けることもひとつの「知性による感情コントロールゲーム」のひとつなのかもしれません。僕の使命は人間の世界を独学で学び続けることなのかもしれません。
にしけい