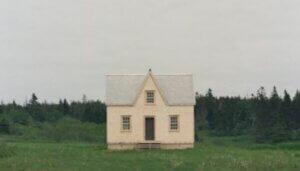北海道では、本州とは異なる環境条件のため、気学や風水の原理がかなり独特に作用します。ブログ記事のタイトルの問いである「北海道でも一般的な気学や風水の考え方は通用するのか?」に対して、「めちゃくちゃ通用する部分」と「全く通用しない部分がある」というのが僕の結論になります。
具体的すぎることや個別の吉凶について書くと誤解を招くので避けますが、「めちゃくちゃ通用する部分」と「全く通用しない部分」について、簡単にまとめたいと思います。
めちゃくちゃ通用する部分
本州では発生しにくくて、北海道で起きやすい現象のひとつに「境界性の強化」というものがあります。
・土地が広い
・隣家までの距離が遠い
・雪が降る
・断熱材による高機能化
これらは「境界性の強化」を高める作用があり、北海道の住宅では本州の住宅に比べてこれらの要素が出てきやすいです。
狭い土地に比べて、北海道では境界性が強くなる傾向があります。特に戸建ての場合、家や土地の影響はとても強く出ます。それぞれの家で独特の文化や思考が醸成され、隣家の影響をあまり受けないんですね。その結果、その家や土地がもっている固有の現象が強く出るんですね。
この特性により、いい家と悪い家の差が極端になりやすく、世代間での影響格差も大きくなります。例えば、祖父の代は隆盛していても、子や孫の代で大きく衰退するというケースが見られます。田舎あるあるかもしれませんが、北海道の場合はその差がかなり顕著です。これは北海道の地形自体が作り出す境界性の強さに依存していると考えられます。
全く通用しない部分
一方で、従来の気学や風水の考え方が全く通用しない部分もあります。
・屋根が雪国仕様
・家の形が独特
・農地や倉庫など変則要素が多い
・お墓や家系の影響が強い
→家の間取り図や旧来の見方では説明がつかないこと結果を招くことが多い
特にお墓や家系といったバックグラウンドの影響は大きいです。北海道自体が街によって様相や雰囲気が大きく異なるのですが、さらに「北海道への関与の仕方」がそれぞれ異なる点も大きいです。開拓のために先祖が移り住んだパターンもあれば、元々アイヌの血筋で現地の人と交わったパターンなどもありますし、移民同士の結婚で続いている家系もあります。
似たような家や建物を建てても、そこから選択される方向性がバックグラウンドによって異なるわけです。キンモクセイの香り自体は同じ成分だったとしても、それを嗅いだときにどのような情景や感情を想起するかが個々で異なるように、大雑把に括れない要素が多分にあるのです。
お墓の文化自体は関東圏と似た形状のものが多いですが、建てる場所や大きさが他の都道府県とは異なる傾向がありますし、使い放題の土地でやたらめったら大きなお墓が作られる場合もあります。
家や土地を見る上で古典的な理論を押さえておくことは必須ですが、単なる知識だけでなく、実際の状況を観察することがとにかく大事ですし、時代に合わせて柔軟に捉え方を変える必要もあります。
北海道での気学や風水は、本州とは異なる独自の発展を遂げつつあり、境界性の強さによって「そのまんま出る」場合もあれば、家系やバックグラウンドの観察と併せて繊細な判断を求められる場合があります。最近だと、移住者やインバウンドの要因なども入ってくるので、毎回多様化が進んでいることを感じさせられる面白い地域です。
にしけい